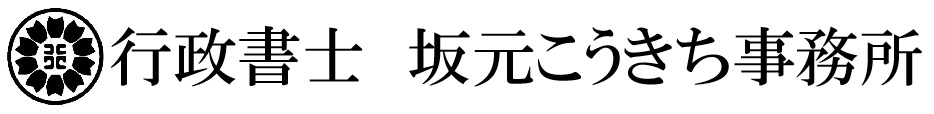在留資格とは、外国人が人本に合法的に滞在し、特定の活動を行うために必要な法的資格のことです。日本の『出入国管理難民認定法』に基づいて定められており、活動内容や身分に応じて様々な種類があります。
- 1 在留資格の種類について
- 1.1 就労資格一覧(入管法一の表)
- 1.2 上陸許可基準適用の就労資格一覧(入管法二の表)
- 1.3 非就労在留資格(三の表)
- 1.4 上陸許可基準適用の非就労在留資格(四の表)
- 1.5 五の表
- 1.6 入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
- 1.7 在留資格該当性とは
- 1.8 基準適合性とは
- 1.9 『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の違い
- 1.10 犯罪歴など特別な問題がないこと
- 1.11 申請する在留資格の特定
- 1.12 在留資格の虚偽申請について
- 1.13 所属機関のカテゴリーについて
- 1.14 入国・在留手続きの流れについて
- 1.15 在留資格認定証明交付申請
- 1.16 在留資格変更許可申請
- 1.17 在留期間更新許可申請
- 1.18 在留資格取得許可申請
- 1.19 永住許可申請
- 1.20 資格外活動許可申請
- 2 お問い合わせ
在留資格の種類について
在留資格の種類は大きく分けて、『就労系在留資格』、『身分・地位に基づく在留資格』、『文化・教育系在留資格』、『技能実習・特定技能』、『その他(特定活動・短期滞在)』などがあります。
まずは就労資格から見ていきます。就労資格とは、外国人が日本国内で合法的に働くために必要な在留資格の一種であり、報酬を伴う活動を認めるものを指します。
資格の種類も職種や活動内容によって分類され、それぞれの就労資格に認められた業務しか行うことができません。
就労資格一覧(入管法一の表)
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に挙げる活動を除く) | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日 |
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く) | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
上陸許可基準適用の就労資格一覧(入管法二の表)
| 在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
該当例 | 在留期間 | |
| 高度専門職 |
1号 |
イ 法務大臣が指定する本法の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 | ポイント制による高度人材 | 5年 |
| ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
| ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
|
2号 |
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 | 無制限 | ||
| ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 | ||||
| ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 | ||||
| ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) | ||||
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
| 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中東教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校、高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転筋、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は30日 |
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦車、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
|
特定技能 |
1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 法務大臣が個々に指定する機関(1年を超えない範囲)。通算で5年 |
| 2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年、1年又は6月 | |
| 技能実習 | 1号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | ||||
| 2号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | ||
| ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | ||||
| 3号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | ||
| ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | ||||
非就労在留資格(三の表)
非就労系在留資格とは、原則として日本国内での就労を目的としない在留資格のことです。つまり、報酬を得る活動(仕事)を行うことが基本的に認められていない在留資格です。
資格外活動許可を取得すれば、四の表の留学生や家族滞在者は週28時間以内のアルバイトが可能ですが、『短期滞在』や『文化活動』は資格外活動許可の対象外であり、一切の就労はできません。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族への訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
上陸許可基準適用の非就労在留資格(四の表)
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受入れられて行う技能等の習得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
| 家族滞在 | 一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
五の表
特定活動とは、法務大臣が個々に指定した活動を行う外国人に与える在留資格です。他の在留資格(就労・非就労・身分など)に当てはまらない、いわば例外的なケースをカバーするための柔軟な制度です。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
居住資格とは、日本の在留資格のうち、外国人の『身分』や『地位』に基づいて与えられる在留資格を指します。これは『活動資格』(特定の仕事や学業などの活動に基づく資格)とは異なり、活動制限がなく、原則としてどんな仕事にも就くことができます。
| 在留資格 | 本邦において有する身分または地位 | 該当例 | 在留期間 |
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の『特別永住者』を除く。) | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
以上が外国人が取得できる在留資格となり、これらの在留資格に該当しない若しくは証明できない場合は、日本で活動及び居住することができません。
次項で日本で活動及び居住するための大事な立証要件である、『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を見ていきます。
在留資格該当性とは
『在留資格該当性』とは、外国人が日本で行おうとしている活動が、入管法で定められた在留資格のいずれかに該当するかを判断する基準です。それぞれの在留資格の活動内容は、上記の在留資格一覧の『本邦において行うことができる活動』欄をご覧ください。
在留資格の申請人が希望する在留資格があったとしても、その活動内容の業務に従事しないのであれば申請は認められません。それは勤務先が大企業であっても、あるいは申請人が高度な専門知識を要する仕事に就こうとしていても同様です。
在留資格の申請をする際には、必ず申請人が行おうとする活動(職務内容)が、申請しようとする在留資格の活動に合致しているか、すなわち在留資格該当性があるか検証する必要があります。
例)
・『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で申請する場合
⇒その活動が『技術職』や『翻訳・通訳』など、該当する業務である必要があります。
該当しない例)
・『技術・人文知識・国際業務』で申請しているのに、実際は単純労働(清掃や倉庫作業など)を行う予定
⇒在留資格該当性なし⇒不許可の可能性大
基準適合性とは
『基準適合性』とは、在留資格認定証明書の交付を受けるために必要な諸条件を定めた法務省令を満たしているかを判断する基準です。本来は、現在海外に居住する外国人が来日して就労を開始する場面に用いられます。すなわち、上陸のための基準を示すものですが、在留資格を許可されて日本に居住している外国人が、その在留資格を変更または更新するときにも準用されます。
例)
・『技術・人文知識・国際業務』の場合
⇒大学卒業(または10年以上の実務経験)+日本人と同等以上の報酬などの条件を満たす必要がある
適合しない例)
・高卒で実務経験もない⇒基準適合性なし⇒不許可の可能性あり
『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の違い
| 項目 | 在留資格該当性 | 上陸許可基準適合性 |
| 審査対象 | 活動内容が在留資格に合っているか | 学齢・経験・報酬などの条件を満たしているか |
| 対象資格 | 全ての在留資格 | 一部の活動類型資格(就労系・留学など) |
| 位置づけ | 入管法上の基本要件 | 追加の審査基準 |
『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の両方を満たさないと不許可になりますが、『在留資格該当性』がなければ、そもそも審査対象外となり、『上陸許可基準適合性』がなければ、『在留資格該当性』が満たされていても不許可になる可能性があります。
入国在留関係手続きの審査は、基本的には書面審査ですので、たとえ実態として『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』があったとしても、それを提出資料により立証できないと在留資格は許可されません。
このように在留資格を得るためには、書面審査をクリアするために必要とされる書類の作成と必要資料の準備、そして作成した書類で『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を立証できることが重要です。いくら書類リストに載っている書類を全て提出したところで、提出書類で『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』が立証できていなければ意味がありません。
また仮に『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を書面で立証できたとしても、申請人に重大な犯罪歴や特別な問題があれば、在留資格は許可されません。
犯罪歴など特別な問題がないこと
この特別な問題には、(1)犯罪歴、(2)税金の滞納、(3)加入義務がある健康保険等への未加入若しくは保険料等の未払い、(4)各種届出の未履行、(5)所属機関の経営難等、(6)外国人採用の必要性が認められないこと、(7)申請内容の信憑性が認められないこと等があります。
申請する在留資格の特定
在留資格は、一般的に『ビザ(査証)』と呼ばれることが多いですが、両者は別物です。ビザが日本政府(外務省、在外公館)の発行する入国のための推薦状のようなものであるのに対し、在留資格は日本に滞在しつつ、それぞれの資格ごとに法定された活動を行うことを認める日本政府(法務省)の許可です。ビザは、海外にある在外公館においてしか発給されません。
在留資格を特定する際によくある間違いは、申請人の学歴や職歴からどの在留資格なら許可を得られそうか?という視点で在留資格を特定しようとすることです。しかし、そもそも在留資格は入管法所定の活動を行うために申請するものです。すなわち、入管法はその別表第一、第二においてこのような在留資格を有する者はこのような活動ができるということを在留資格ごとに定めています。
そこで申請人の学歴・職歴からするとどの在留資格が取れるだろうか?と考えるのは論理が逆で、まずは申請人が日本で行う活動を確認し、その活動を行える在留資格はどの在留資格なのか?を考える必要があります。
在留資格の虚偽申請について
よくある相談が、とにかくどんな在留資格でもいいので申請人が日本にいられるようにして欲しいというものです。仮に申請者の学歴・職歴から在留資格が許可されるかもしれませんが、実際に従事する業務がその在留資格の活動内容と異なる場合は虚偽申請にほかなりません。また発覚した場合は下記のペナルティが科せられる可能性があります。
また最終的には申請者自身でも在留資格申請の内容を確認するべきであり、虚偽申請が発覚した場合の影響は本人(申請者)だけにとどまらないと知るべきだと思います。
・発覚した場合の主な影響
| 項目 | 内容 |
| 申請の不許可 | 審査中に発覚した場合、申請は却下されます在留資格の取り消し |
| 在留資格の取り消し | すでに許可されていた場合でも、取り消される可能性があります |
| 刑事罰 | 入管法第70条に基づき、最大で『懲役3年以下または罰金300万円以下』に処されるか併科されます |
| 強制退去 | 虚偽申請が重大と判断された場合、退去強制の対象となります |
| 再入国禁止 | 一定期間、日本への再入国が認められなくなる可能性があります |
・関係者にも影響が及ぶ
- 虚偽申請を手助けした行政書士や企業担当社も『営利目的在留資格等不正取得助長罪』に問われる可能性があります。
- 家族や配偶者の在留資格にも影響することがあります。
・予防と対策
- 申請内容は必ず本人(申請者)が確認すること
- 専門家に依頼する場合でも書類の内容を把握しておくこと
所属機関のカテゴリーについて
在留資格及び必要な手続きの特定ができたら、申請人が所属する機関がどのカテゴリーに分類するのかを特定します。この段階でカテゴリーを特定する意味は2つあります。
まず1つ目は、各地方出入国在留管理局によっても異なりますが、カテゴリーによって大きく審査機関に違いが出る場合があることです。
在留資格認定証明書交付申請の場合、所属機関がカテゴリー1・2である場合とカテゴリー3・4の申請では、カテゴリー1・2の審査機関より更に1ヶ月程度審査が長引きます。
2つ目は、カテゴリー1・2とカテゴリー3・4では申請手続きの提出書類と費やす時間が大きく異なるため、費用も変わってくると思います。では、それぞれのカテゴリーの区分を見ていきましょう。
・所属機関のカテゴリー一覧
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
| 区分(所属機関) |
次のいずれかに該当する機関 (1)日本の証券取引所に上場している企業 (2)保険業を営む相互会社 (3)日本又は外国の国・地方公共団体 (4)独立行政法人 (5)特殊法人・認可法人 (6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (7)法人税法別表第一に掲げる公共法人 (8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) (9)一定の条件を満たす企業等 |
次のいずれかに該当する機関 (1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の現徴収額が1,000万円以上ある団体・個人 (2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
まず、カテゴリー1に分類されるのが東証プライム上場の株式会社です。ネット検索ですぐにその会社が上場しているかについて確認できると思います。
また、保険サービスを行う会社のうち、株式会社ではなく相互会社に分類される会社や、独立行政法人等、大会社であったり、公共機関であったりと、その多くは正式名称を聞くだけでカテゴリー1に当てはまるか否かを判別しやすい機関となります。
カテゴリー2・3は、カテゴリー1・4に当てはまらない機関のうち、前年度の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』に記載された給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の場合はカテゴリー2に、それ未満の場合はカテゴリー3となります。たとえ1円の差であっても、どちらに分類されるかによって雲泥の差となり、カテゴリー3に分類されてしまうと、カテゴリー2の場合の何倍も書類を提出する必要があります。
カテゴリー2に分類される機関は、従業員が数十名以上の、ある程度の規模の中企業~上場していない大企業までとなりますが、あくまで分類の基準は機関が社員に支払う給与額に対する源泉徴収税額の合計となるため、中には従業員1人1人の給与額が高額出あるために、数名規模の機関でもカテゴリー2に分類される場合もあります。
カテゴリー4に分類されるのは、主に新設の機関となります。給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、各機関が1年に一度、年始に税務署に提出しますが、この合計表の提出がされていない新設機関等がカテゴリー4となります。
入国・在留手続きの流れについて
入国前の在留資格申請から入国後に発生する手続きの流れです。手続きを行う官公署にも注意しましょう。
| 日本入国前 | 日本入国後 | |||
| 在留資格認定証明書 | 査証(ビザ) | 上陸許可 | 在留期間更新許可 | 在留資格変更許可 |
|
申請取次、受入機関等(又は外国人本人)が在留資格認定証明書交付申請を行い、交付を受けます。 ⇒ ※『短期滞在』、『永住者』を除く。 |
外国人本人が査証(ビザ)申請を行い、発給を受けます。 ⇒ ※査証免除措置による入国を除く。 |
到着した空海港において、入国審査官による上陸審査を受け、上陸許可を受けます。 ⇒ (空海港のある地方入管で) |
在留期間を超えて日本に在留することを希望する場合は、在留期間更新許可申請を行い、許可を受けます。 ⇒ (地方入管(空海港を除く)で |
在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、在留資格変更許可申請を行い、許可を受けます。 (地方入管(空海港を除く)で |
在留資格認定証明交付申請
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(『短期滞在』及び『家族滞在』を除く)に該当するものである等の上陸のための条件にてきごうしていることを証明するために入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
在留資格変更許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
この手続きにより、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるように申請することができます。
在留期間更新許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを定めています。
在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続きを受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認められていますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の申請をしなければなりません。
永住許可申請
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者または出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更または永住者の在留資格取得を希望する場合に行う申請です。
永住許可を受けた外国人は、『永住者』の在留資格により日本に在留することになります。在留資格『永住者』は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続きとは独立した規定が特に設けられています。
資格外活動許可申請
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。資格外活動の許可は、『認印シール(パスポートに貼付)』または『資格外活動許可書』の交付により受けられます。
認印シールまたは資格外活動許可書には、『新たに許可された活動内容』が記載されますが、(1)雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合、(2)原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合、(3)地方公共団体等において雇用されている『教育』、『技術・人文知識・国際業務』または『技能(スポーツインストラクターに限る)』の在留資格をもって在留する外国人が、1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて、在留資格『教育』、『技術・人文知識・国際業務』または『技能(スポーツインストラクターに限る)』に該当する活動を行うことを条件として、勤務先の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合((2)及び(3)の場合を『包括的許可』といいます)があります。
また手続き先についてもオンラインが増えているとはいえ、窓口の入国管理局も平日の日中に行かなければなりません。
弊所ではお客様に代わり、面倒なお手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。