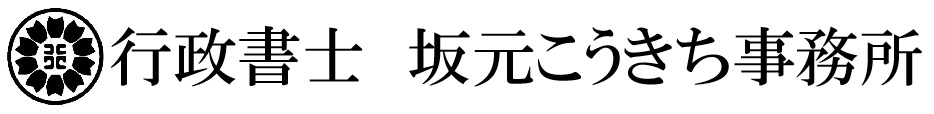相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)の財産(預貯金・不動産・有価証券など)や権利義務を、法律に基づいて指定された人が引き継ぐために行う一連の法律的・行政的手続です。
ご家族が亡くなったとき、日常生活が一変し目の前の手続きをこなすだけでも大変です。
法的手続きや役所や金融機関での手続きをしないといけないことはわかるけど、私の場合はどうなるの?
手続きの方法は?遺言書があったとき、なかったとき、だれに相談したらいいの?など悩みの種はつきません。

誰しも必ず直面する相続手続き。そもそもどのような準備をしていけばいいのでしょうか。
- だれが財産を相続するのか
- 相続財産の調査
- 法律上の手続き・その他重要な手続き
- どのような流れで手続きするのか
やらないといけないことは山盛りです。ひとつひとつ見ていきましょう。
だれが財産を相続するのか(相続人の確定)

故人に配偶者と子供がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また相続人の第1順位である子供も相続人となります。故人を中心に相続範囲をシミュレーションすると下記の図になります。これは法律で決められた相続人の範囲(基準)を示すものです。
ただし遺言書があったり、相続人間で話し合い(遺産分割協議)が合意すれば、違う人が相続人になったり、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

法定相続分について

遺言による相続分や遺産分割の方法の指定がない場合、民法による相続分の定め=法定相続分に従って遺産分割が行われます。法定相続分の割合は相続人の構成により異なります。
|
配偶者 |
1/2 | 2/3 | 3/4 | 全部 | / | / | / | / | / | / | / |
|
子(第1順位) |
1/2 | / | / | / | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | / | / | / |
| 親 (第2順位) |
0 | 1/3 | / | / | 0 | / | / | / | 全部 | 全部 | / |
| 兄弟姉妹 (第3順位) |
0 | 0 | 1/4 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 全部 |
相続財産の調査

相続人の確認と並行して、相続財産の調査も必要になります。把握しているご本人はすでにいませんので、ご家族が確認していくことになります。主な財産は下記になります。
故人が遺言書やエンディングノートに財産の詳細を明記していれば、ご家族の負担は軽減されると思います。このようなパターンはまだまだ少ないのが現状です。
またご家族が亡くなって失意の中で財産調査に手を付けられないという方が多いように見受けられますが、財産の調査と並行して法的手続きの期限についても注意が必要です。期限を過ぎるとペナルティや不利益が発生します。
・財産調査一覧
| 財産の名称 | 財産の例 |
| 預貯金・現金 | 普通預金・定期預金・定額預金など |
| その他の金融資産 | 株式・投資信託・生命保険・損害保険など |
| 土地・不動産 | 持ち家・家の土地(固定資産税評価額や路線価)・不動産事業など |
| その他の財産 | 自動車・骨董品・宝石など |
| マイナスの財産 | 借金など |
・期限のある財産相続・税申告手続き
| 手続き・申告名 | 内容 | 処理期限 |
| 相続放棄 |
故人の財産を一切相続しない。マイナス財産がプラス財産より多い場合にメリットがある。 |
3ヶ月以内 |
| 限定承認 | 個人のプラス財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。 | 3ヶ月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 故人の所得税の申告を相続人が代わりに行う。通常の確定申告とは異なり、死亡した年の1月1日から死亡日までを申告。 | 4ヶ月以内 |
| 相続税申告 | 故人の財産を相続・遺贈によって取得した人に課される税金 | 10ヶ月以内 |
法律上の手続き

法律上の手続きは多岐にわたり複雑であるため、上記と重複しますが、わかりやすく一覧にてご案内します。
| 手続き名 | 手続き先 | 備考 |
| 相続人の確定(相続関係説明図の作成) | 市区町村役場 | 市区町村役場で謄本等を蒐集して相続人や専門家が作成 |
| 遺産の調査(遺産目録の作成) | 引き継ぐ手続き先全て | 現金・預貯金・金融資産・土地・不動産・マイナスの財産等 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人 | 相続人で話し合い、協議書に署名捺印をする |
| 特別代理人選任の申立(相続人が未成年の場合) | 家庭裁判所 | 親権者や後見人などの法定代理人が申し立てる。司法書士や弁護士の代理申請も可能 |
| 遺言書の検認手続き(自筆証書遺言) | 家庭裁判所 | 申請から2週間ほどかかる |
| 遺言執行者選任の申立(遺贈の場合) | 家庭裁判所 | 相続人、受遺者、遺言者の債権者が申し立てる |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 3ヶ月以内に申述 |
| 不動産の名義変更登記(相続登記) | 法務局(司法書士) | 遺産分割協議書など必要書類を揃えて司法書士へ依頼 |
| 会社役員の死亡登記 | 法務局(司法書士) | 許認可要件と絡むため、速やかに手続き |
| 住宅ローンの引受け | 金融機関・法務局 | ほとんどの住宅ローンでは契約者が死亡した場合に備えて『団体信用生命保険』に加入している。未加入の場合は、相続人が引受ける |
| 根抵当権の引受け(事業用資金の借入がある場合) | 金融機関・法務局 | 原則として法定相続分に応じて相続人が引受ける。6ヶ月以内に処理しないと元本確定され、通常の抵当権と同じ扱い |
| 借金の整理 | 債権者(司法書士・弁護士) | マイナスの財産も相続財産となる |
| 遺留分減殺請求 | 相続人 | 遺言や生前贈与によって法定相続人の最低限の取り分が侵害された場合に請求。時効に注意 |
| 所得税の準確定申告(被相続人) | 税務署(税理士) | 故人の所得税の申告を相続人が代わりに行う。通常の確定申告とは異なり、死亡した年の1月1日から死亡日までを申告。 |
| 所得税の確定申告(相続人) | 税務署(税理士) | 相続によって財産を取得した場合、所得税の申告は不要(相続税が対象)ですが、所得税の申告が必要になるケースもある |
| 消費税の届出書 | 税務署(税理士) | 故人が個人事業主で課税事業者の場合で、相続人がその事業を引き継いだ場合と準確定申告が必要な場合も届出が必要。 |
| 相続税の申告 | 税務署(税理士) | 故人の財産を相続・遺贈によって取得した人に課される税金 |
| 事業の許認可(農業・建設業・酒・たばこの販売等) | 管轄官庁 | 事業引継の申請期限があるが、許認可を相続できる。期限が短く間に合わないときは、一度廃業して新規登録 |
| 特許権 | 特許庁(弁理士) | 相続財産として著作物の複製・上映・配信などで収益を得る権利を相続できる |
その他重要な手続き(実務・生活関連)
家族が亡くなった際に行う手続きのうち、上記の法律上の手続き以外は一般的に『死亡後の実務手続き』や『生活関連の手続き』と呼ばれます。これらは生活の整理や社会的な対応としてとても重要です。
基本的な事務手続き

家族が亡くなった後の事務手続きも多岐にわたります。事務処理期限がある手続きが多いので一つ一つ確実に進めていきましょう。
| 手続き名 | 届出場所 | 備考 |
| 死亡届 | 市区町村役場 | 7日以内に届出 |
| 死体火葬(埋葬)許可交付申請 | 市区町村役場 | 一般的に死亡届と同時に提出。7日以内届出 |
| 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 14日以内に届出 |
| 児童扶養手当認定請求 | 市区町村役場 | 世帯主変更届と同時に提出 |
| 児童手当・児童扶養手当の異動届 | 市区町村役場 | |
| 復氏届 | 市区町村役場 | 婚姻前の氏へ戻す手続き |
| 姻族関係終了届 | 市区町村役場 | 婚姻関係は自動的に終了しますが、姻族関係を終了させる場合に必要 |
| 子の氏変更許可申請 | 家庭裁判所 | 親が旧姓に戻っても子供の氏は自動変更しない |
| 国民健康保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | 14日以内に届出 |
| 国民年金の死亡届 | 市区町村役場 | 7日以内に提出 |
| 年金受給者死亡届 | 年金事務所 | 14日以内に届出 |
| 介護保険証の返還 | 市区町村役場 | 14日以内に返還 |
| 敬老優待乗車証の返還 | 地区町村役場 | 期限はありませんが、速やかに返却 |
| 死亡退職届 | 勤務先 | 速やかに届出 |
| 最終給与の手続き | 勤務先 | 支給日の到来日によって税金対象が変わる |
| 身分証明書の返還 | 勤務先 | 速やかに返却 |
| 健康保険証の返還 | 勤務先 | 速やかに返却 |
もらう手続き

家族が亡くなったときに『もらえる手続き(給付・支給)』には、公的制度に基づく給付金や還付金があります。以下に代表的なものをご案内します。
| 手続き名 | 届出場所 | 備考 |
| 生命保険・医療保険 | 保険会社 | 生命保険と医療保険の請求手続き。請求期限あり |
| 簡易保険 | 郵便局 | かんぽ生命保険の請求手続き。請求期限あり |
| 団体弔慰金 | 互助会・協会・サークル | 勤務先の企業や団体が遺族に支給する金銭 |
| 死亡退職金 | 勤務先 | 遺族が受け取る退職金の代わり。退職金と両方はもらえない |
| 葬祭費・葬祭給付(国民健康保険) | 市区町村役場 | 故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していると申請できる |
| 埋葬料・家族埋葬料(共済) | 共済組合 | 組合員が公務外で死亡したときに申請できる |
| 葬祭料・葬祭給付 | 労働基準監督署 | 労災保険に加入し業務災害や通勤災害で亡くなった場合の給付 |
| 遺族基礎年金(国民年金) | 市区町村役場 | 国民年金加入者が死亡し、その人によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』に支給される |
| 遺族厚生年金(厚生年金) | 年金事務所 | 厚生年金加入者が死亡し、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される |
| 遺族共済年金(共済年金) | 共済組合 | 公務員など共済組合に加入していた方がなくなった際に遺族に支給される |
| 遺族(補償)年金・一時金 | 労働基準監督署 | 労働者が業務上の災害で亡くなった場合に遺族に支給される年金給付 |
| 寡婦年金(国民年金) | 市区町村役場 | 国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなった場合に子のいない妻に支給される |
| 死亡一時金(国民年金) | 市区町村役場 | 国民年金第1号被保険者が亡くなった際に一定の条件を満たす遺族に一時的に支給される |
| 高額療養費(国民健康保険) | 市区町村役場 | 医療機関での支払いが一定の限度を超えた場合にその超過分が払い戻される |
| 高額療養費(健康保険) | 全国健康保険協会・健康保険組合) | 医療機関での支払いが一定の限度を超えた場合にその超過分が払い戻される |
| 高額療養費(共済) | 共済組合 | 医療機関での支払いが一定の限度を超えた場合にその超過分が払い戻される |
引き継ぐ手続き

家族が亡くなったときには役所・金融機関・保険など故人の契約や制度を引き継ぐものと、遺族が新たに加入・変更するものに分かれます。
| 手続き名 | 届出場所 | 備考 |
| 借地契約 | 貸主 | 借主が亡くなった場合、契約は自動終了せず、財産権として相続の対象となる |
| 賃貸住宅 | 管理会社・貸主 | 借主が亡くなった場合、契約は自動終了せず、借主の賃借権・敷金返還請求権・家賃債務などは相続人に引き継がれる |
| 公営住宅 | 公営管理団体 | 公営住宅は生活に困窮する低所得者向けに提供される住宅なので、契約は相続されず自動的に引き継がれることはない |
| 火災保険等 | 損害保険会社 | 自動的に契約終了しませんが、名義変更などの手続きが必要 |
| 預金・貯金 | 金融機関・法務局 | 原則として相続財産として扱われる。口座は凍結され、相続手続きにより分配される |
| 出資金 | 信用金庫・農協等 | 信用金庫・農協等に連絡し、死亡による脱退手続きによる払戻しか名義変更が可能 |
| 株式 | 証券会社・証券代行 | 株を売却する場合でも一旦相続人の口座に引き継ぐ |
| 自動車 | 陸運局 |
相続による移転登録(名義変更)手続き |
| 自動車保険 | 損害保険会社 | 自動的に契約終了しませんが、名義変更などの手続きが必要 |
| 保証金 | 保証金の預け先 | 賃貸契約における保証金(敷金・礼金など)は契約者の死亡によって契約が終了する場合、相続人が返還請求できる |
| 貸付金 | 貸付先 | 相続財産として相続人に引き継がれる。相続人が新たな債権者となり、相続人に返済義務がある |
| 電話加入権 | 電話会社 | 電話加入権は相続財産として扱われ、相続人に引き継がれる |
| 水道光熱費 | 電力会社・ガス会社・水道局 | 自動的に契約は終了せず、相続人が名義変更または解約の手続きを行う |
| 会員権 | ゴルフ・リゾートクラブ |
原則として相続財産として扱われる。ただし会則によっては『死亡=退会』と定めている場合は、預託金の返還請求権のみが相続対象となる |
| 事業の許認可 | 管轄官庁 | 事業引継の申請期限があるが、許認可を相続できる。期限が短く間に合わないときは、一度廃業して新規登録 |
| 著作権 | 各著作権協会 | 相続財産として著作物の複製・上映・配信などで収益を得る権利を相続できる |
| 借金(住宅ローン・クレジット) | 金融機関・法務局・ローン会社 | 負の財産として相続人に引き継がれる。相続人は単純承認・相続放棄・限定承認から選択 |
| 保証人の地位 | 債権者 | 原則として相続人に引き継がれる。主債務者が返済できない場合、相続人が返済義務を負う |
| 固定資産税・都市計画税等 | 市区町村役場 | 毎年1月1日時点の所有者に対して税金が課税される。その時点でなくなっていた場合、相続人が納税義務者となる |
やめる手続き

家族が亡くなった場合、遺族が行う『やめる手続き』は非常に多岐にわたります。以下に死亡後に必要な主な『解約・停止・変更』手続きをご案内します。
| 手続き名 | 内容 | 手続き先 | 期限目安 |
| クレジットカード | 利用停止・解約 | カード会社 | できるだけ早く |
| 銀行口座 | 解約・凍結 | 各銀行 | 速やかに |
| 公共料金(水道・電気・ガス) | 名義変更または解約 | 各契約会社 | 2週間以内が目安 |
| 携帯電話・インターネット | 解約または名義変更 | 通信会社 | 2週間以内が目安 |
| サブスクリプション(Netflix等) | 解約 | 各サービス | 速やかに |
| 運転免許証 | 返納 | 警察署 | 早めが望ましい |
| パスポート | 返納 | 旅券事務所 | 任意 |
| 健康保険証 | 返却・資格喪失届 | 地区町村役場 | 14日以内 |
| 年金受給 | 停止・未支給分請求 | 年金事務所 | 10~14日以内 |
| 雇用保険 | 受給資格証の返還 | ハローワーク | 1ヶ月以内 |
| 介護保険 | 資格喪失届 | 市区町村役場 | 14日以内 |
相続手続きの流れ
相続は被相続人の死亡をもって開始し、相続手続きは遺言書が『ある』場合と『ない』場合で手続きが大きく変わります。2パターンの相続手続きの流れを図解でみてみましょう。

遺言書があると『遺産分割協議』をする必要がないので手続きも後半スムーズですね。
手続きの違いは下記の『遺言書による相続手続き』と『遺産分割協議による相続手続き』をご覧ください。
こんなことでお悩みではありませんか?
- そもそもだれに相談したらよいかわからない。
- 家族が亡くなり部屋から遺言書が見つかった。どうしたらよいかわからない。
- 故人の遺産を相続人で分配したいがどうしたらよいかわからない。
- 相続財産の中に不動産があり、どう手続きしたらよいかわからない。
- 故人名義の預貯金口座が凍結され、預金解約ができない。
- 仕事が忙しく、役所や金融機関が開いている平日に相続手続きを進める時間がとれない。
当事務所では、正確な相続人の特定のための戸籍収集から始まり、財産調査、各種財産の名義変更・解約手続きから財産の各相続人への分配手続きまで総合的にサポートいたします。
※不動産登記や相続税が発生する場合は、提携先の司法書士・税理士が担当致しますのでご安心ください。
相続手続きは、主に遺言書がある場合と遺言書がなく遺産分割協議を行う場合と2パターンあります。
また手続き先の官公署や金融窓口も平日の日中に行かなければなりません。
弊所では家族が亡くなられたお客様に代わり、お手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。