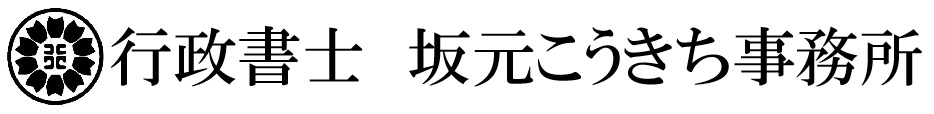定款とは
定款は会社のルールを決めた規則集です。
定款には「会社の商号」や「本店所在地」などの基本情報のほか、「株主総会はいつ開くのか」「決算期はいつにするのか」「取締役は何名にするのか」など、さまざまなことを決めて記載することができます。
定款の作成から認証までの流れ
定款を作成するのは発起人です。発起人全員で作成し、公証役場で認証を受けます。認証とは、「正当な手続きによってなされたことを公の機関が証明する」ことです。
株式会社の定款は、公証人の認証がなされていないものは効力を有しません。定款は会社のルールを決めた大事なものなので、後日の紛争を防ぐため、また内容を明確にするために公証人の認証を経なければ登録を申請することも出来ません。
| 定款の作成から認証までの流れ |
| 1.定款の作成に必要な事項を決める |
| 2.発起人の印鑑証明書および実印を用意する |
| 3.定款を作成する |
| 4.公証役場で事前に定款の確認をしてもらう ※公証役場のメールアドレスへ定款案と資料を送付 |
| 5.公証役場へ行って、正式に定款の認証をしてもらう |
| 6.定款の謄本と控えを取得する |
定款に記載する事項と一般的な定款の構成
定款に記載する事項は大きく分けて次の3つの種類があります。
1.記載しておかないと無効になる「絶対的記載事項」
2.決めたら記載しておかなければならない「相対的記載事項」
3.記載するかどうかは自由である「任意的記載事項」
絶対的記載事項は必ず決めなければいけませんが、それ以外は発起人次第で、会社独自のオリジナルの定款を作ることができます。
定款は、一般的には6~7つの章に分かれ、記載する内容を分類しています。各章に表題をつけ、第1章は「総則」といい、会社の商号や本店、目的など会社の基本情報を書きます。最終章は「附則」となります。
●一般的な定款の構成
| 章 | 表題 | 記載する項目 | 説明 |
| 第1章 | 総則 |
・商号 |
会社の基本情報を記載する。 総則を見れば、その会社がどのような会社かわかる |
| 第2章 | 株式 | ・発行可能株式総数 ・株式の譲渡制限の規定 ・株主名簿の記載(書換え)の請求など |
株式に関する取り決めを記載する |
| 第3章 | 株主総会 | ・開催時期 ・招集の方法 ・決議要件 ・議事録 など |
会社の重要な意思決定機関である株主総会の開催、運営や決議について記載する |
| 第4章 |
取締役および代表取締役 ※取締役会設置会社の場合は、「株主総会以外の期間」 |
・役員の人数 ・役員の任期 ・役員の報酬 など |
役員について記載する。取締役会および監査役を配置している会社の場合、第4章にまとめて記載してもよいが、別に章を設けて記載してもかまわない |
| 第5章 | 計算 | ・事業年度 ・剰余金の配当 など |
会社の決算などについて記載する |
| 第6章 | 附則 |
・設立時の資本金額 |
第5章までに記載する事項以外のことは附則に記載する。設立の際に特有の取り決めは附則に記載する |
絶対的記載事項とは
『絶対的記載事項』とは、その名の通り絶対に決めておかねばならないことです。
定款の中に必ず入れておかなければならいないことを『絶対的記載事項』といいます。下表の5つの事項が記載されていない定款は無効になってしまい、公証人から定款の認証を受けることができません。
絶対的記載事項は、会社の柱となる重要な事項です。既存の会社の情報をそっくりそのまま真似すればいいというものではありません。それぞれの会社の実情、方向性にあった内容になるように検討しましょう。
●絶対的記載事項
| 絶対的記載事項 | 内容 |
| 目的(会社の事業目的) | どのような事業を行うのか記載する |
| 商号 | 会社の名前 |
| 本店の所在地 | 定款には本店住所のうち、最小行政区画である市区町村まで(政令指定都市は市までなど)を記載すればかまわない。住所全てを記載してしまうと、引っ越しをする度に定款を変更する必要がある |
| 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 | 会社の資本金となる出資額を決める。定款では『○○円以上』と最低額を記載しても構わないが、出資額を『○○円』と決定しておくほうが、書類作成が楽に進む。 |
| 発起人(出資者)の氏名または名称およびその住所 |
お金を出す出資者のことを、定款では『発起人』という。個人でも法人でも発起人になることが可能。法人の場合は、名称および本店住所を定款に記載する |
相対的記載事項とは
『相対的記載事項』とは、定款に記載しておかないと有効にならないことです。
定款の記載事項の中には、『相対的記載事項』という決めても決めなくてもよいけれど、決めたなら定款に記載しないと有効にならない事項があります。
絶対的記載事項のように記載しないと定款自体が無効になるわけではありませんが、定款に記載しなければ意味がありません。
●相対的記載事項
| 相対的記載事項 | 内容 |
| 株式の譲渡制限に関する規定 | 株式を譲渡する場合に会社の承認を必要とする旨の規定。会社が知らない間に株式の譲渡があり、会社の経営とは関係のない第三者が株主となるのを防ぐことができる。中小企業の多くがこの規定を設けている |
| 株主総会などの招集通知を出す期間の短縮 | 株主総会を招集するには通常は2週間前までに招集通知を出さなければならないが、短縮することもできる |
| 役員の任期の伸長 | 会社法では取締役の任期は2年だが、株式の譲渡制限規定を設けていれば10年まで延ばすことができる |
| 株券発行の定め | 株券は発行しないのが原則だが、発行する場合は定款に記載して株式を得ることができる |
| 現物出資 | 現金以外にも不動産や有価証券、パソコン、車などを出資して株式を得ることができる |
| 財産引受 | 会社の設立を条件として会社は発起人から事業用の財産を譲り受ける契約をすることができる |
任意的記載事項とは
『任意的記載事項』とは、定款に記載してもしなくてもいいことです。
相対的記載事項と同じように決めても決めなくてもいい上に、決めたとしても定款に記載してもしなくてもいい事項を任意的記載事項といいます。
任意的記載事項は定款に記載する義務はありませんが、定款内で定めることで明確になるので、記載することをおすすめします。
●任意的記載事項
| 任意的記載事項 | 内容 |
| 事業年度 | 会社の決算期を決める。決算期を決めることは義務ではありませんが、法人税法上では、1年に1回以上の決算が必要 |
| 取締役等の役員の数 | 取締役などの役員の数は取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上いればよく、取締役会を設置している会社になると取締役が3名以上と監査役が1名以上必要。 |
| 株主総会の議長 | 株主総会における議長を誰がやるか、またはどのように議長を決めるかを記載する |
| 定時株主総会の招集時期 | 定時株主総会は決算を迎えた後の一定の時期に招集しなければならないので、その時期を記載する。毎事業年度の終了後2ヶ月以内または3ヶ月以内とすることが多い。特に希望がなければ『3ヶ月以内』とする |
| 基準日 | 株式会社は一定の日(基準日)を決めて、その日の時点で株主名簿に記載または記録されている株主を権利(株主総会の議決権)を行使できる株主とする。基準日を決めておかないと、株式の譲渡があった場合、引き渡した側と譲り受けた側とで、どちらが権利行使できる株主であるか混乱してしまうので、決めておく |
認証手続きの流れ
定款の作成が終わったら公証役場で定款の認証を受けますが、発起人全員で公証役場へ行くのが原則です。
●定款認証まで
1.定款の認証を受ける公証役場を決める
公証役場は全国にありますが、どこの公証役場で定款認証をしてもらってもいいわけではありません。会社の本店の所在地を管轄する公証役場の公証人に認証してもらいます。例えば、福岡県筑紫野市で会社を設立する場合は、最寄りの筑紫公証役場がよいでしょう。ちなみに、他の福岡県内公証役場でも認証対応は可能です。
2.事前に公証役場および法務局で定款の内容をチェックしてもらう
公証役場へ定款の認証に行く前に、必ず作成した定款の内容をチェックしてもらいます。各公証役場の電話番号・FAX・メールアドレスが公証役場のサイトに掲載されています。メールで詳細を送った後に電話で『会社を設立するので、定款の認証前に事前確認して欲しい』と伝えましょう。定款の他に、印鑑証明書・実質的支配者となるべき者の申告書・免許証の写し(身分証明書)も一緒に送り、正確な記載がされているか確認してもらいます。
公証役場によっては、内容に問題がなくても表現や言葉を訂正してくれたり、細かい点までチェックしてくれることもあります。
私の場合は、商号に特殊文字が入っていたため、法務局へ使用可能か確認してくださいとアドバイスをいただきました。
3.公証役場へ出向く
定款の内容に問題がなければ、必要なものを揃えて公証役場へ認証を受けに行きます。
また、その他持参するものとして発起人の印鑑証明書(3か月以内のもの)・発起人からの押印済み委任状(定款内容を合綴し、発起人の実印で契印したもの)・実質的支配者となるべき者の申告書・USBメモリ、CD-R、DVD-R等の記録媒体等があります。
定款の認証をする際に公証人が本人確認をするので、公証役場に発起人または代理人が出向かなければなりません。
実際に出向く段階になれば、予定日を公証役場と打ち合わせをして訪問することになります。これは公証人が1人しかいない公証役場だと出張でいないことがあるためです。二度手間にならないよう、事前打ち合わせをして出向くようにしましょう。
公証役場へ定款認証に行くときに持参するもの
1.定款3通
定款は、公証人が認証をした後、3通のうち1通は公証人が公証役場保存用として原本を保管し、1通は会社保存用原本、1通は登記用の謄本として発起人に返却されます。
3通とも発起人全員の署名押印をし、契印も忘れないようにしましょう。押印は必ず個人の実印で行ってください。
2.発起人全員の印鑑証明書:各1通
印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。発起人と役員を兼ねている人は、登記用とは別で用意したほうがいいので、印鑑証明書は各自2通用意します。公証役場へは各1通を持参します。なお、公証役場によっては、印鑑証明書のほか、運転免許証などの本人確認資料の提示を求めるところもあります。
3.収入印紙4万円
公証人保存用の定款に、収入印紙を貼って消印をします。その際、定款に間違いがあるといけないので、公証役場に行って確認をしてもらってから印紙を貼りましょう。収入印紙は公証役場で売っていない場合が多いので、郵便局などで公証役場へ行く前に準備しましょう。
4.認証費用約3~5万2,000円
公証人に支払う費用は、定款の認証費用と謄本代の約2,000円です。定款の認証費用は、資本金の額が100万円未満の場合3万円、100万円以上300万円未満の場合で4万円、300万円以上の場合5万円になります。公証役場の窓口で当日、現金かクレジットで支払います。定款の謄本代は定款の枚数によって変わり、1枚250円なので、一般的な5枚だと1,250円になります。
5.発起人の実印
定款に不備があることも考えて、念のため公証役場へ行く発起人は全員自分の実印を持って行くといいでしょう。
6.代理人に行ってもらう場合は委任状、代理人の印鑑(認印可)、代理人の運転免許証など本人確認できるもの
どうしても公証役場に行くことができない発起人がいる場合は、代理人に頼むこともできますが、会社設立に向けて大事な手続きですから、できるだけ発起人全員で行きましょう。
7.実質的支配者となるべき者の申告書
暴力団および国際テロリストによる法人の不正使用を抑止するため、提出が義務づけられました。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人を指し、以下のいづれかに該当する者になります。
- 株式の50%を超える株式を保有する個人
- ①の該当社がいない場合には、25%を超える株式を保有する個人
- ①②の該当社もいない場合には、事業活動に支配的な影響力を有する個人
- ①②③の該当社もいない場合には、代表取締役
・実質的支配者となるべき者の申告書フォーム(クリックで日本公証人連合会HPへ飛びます)
| 最期にもう一度チェックしよう! |
| 1.定款に発起人全員の署名押印がしてあるか |
| 2.定款は袋とじにしてあるか |
| 3.定款の袋とじ部分に契印がしてあるか |
| 4.押している印鑑は実印か |
| 5.印鑑証明書に記載されている住所・氏名を正確に書いているか |
| 6.印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものか |
| 7.公証役場・法務局で事前にチェックしてもらったか |
| 8.代理人に行ってもらう場合は、委任状と代理人の印鑑を用意したか |
| 9.収入印紙を4万円購入してあるか |
| 10.認証費用52,000円を現金で用意してあるか |
また手続き先の公証役場・法務局等も平日の日中に行かなければなりません。
弊所ではお客様に代わり、面倒なお手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。