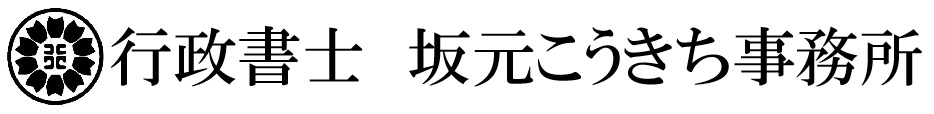公正証書遺言とは

公正証書遺言は、法律専門家である公証人関与のもと作成するので 方式や内容で無効となることはまず考えられません。
管理に関しても公証役場にて保管される為、紛失や偽造の心配もなく 最も安全確実な遺言といえます。
遺言書を公正証書で作成する意味

第三者の『公証人』が関与・作成することで、公文書として扱われることにあります。
公文書とは、国や地方公共団体などの公的機関が作成した文書のことです。
文書として信頼性が高く、紙媒体だけでなく電子データとしても保存されます。
相続発生後に遺産分割が整いそうにないような場合に、遺言を公正証書で 作成しておくことで遺言の法的有効性や内容の明確性を確保することができます。
また、紛争の可能性が少ない家族構成であったとしても、公正証書の遺言で 予め遺産の分け方を確定しておくことで、紛争予防としての効果も発揮します。
もし自筆証書で遺言を作成しておいたとしても、それが本当に遺言者本人の真意であるかどうか疑った 相続人が争いを起こすことも想定されますので、公文書として作成された公正証書遺言は絶対的に「強い」のです。
他方で作成手数料がかかること、公証役場に出向く必要があること、証人2人 を要する等の負担がありますが、特別の事情がある場合を除き上記の理由から 公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言を特に勧める場合

公正証書遺言は、公証人と証人2人の立会いのもと作成されます。
下記のような自書が難しい、身体能力に不安がある場合でも確実な遺言書を作ることができます。
- 遺言の内容が複雑で自分で書くのが困難
- 遺産種類が多くかつ多額
- 法解釈が分かれる事案、公序良俗に反する疑いがある
- 認知能力への不安がある
- 目が見えない、耳が聞こえない、話すことができない、字が書けない等の事情がある場合
公正証書遺言のメリット・デメリット

ここで公正証書遺言のメリット・デメリットをまとめてみましょう。
・メリット
- 遺言が無効になるリスクが低い
公証人は法律の専門家であり、遺言の法的有効性や内容の明確性を確保します。 - 遺言を紛失するリスクがない
公証役場で原本を保管することで、遺言の偽造や紛失を防ぎます。 - 遺言を自分で書く必要がない
文字が書けない場合や遺言の内容が複雑な場合でも、公証人に口頭で伝えれば遺言書を作成できます。 - 遺言の検認が不要
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要なので、遺言者の死亡後すぐに相続手続きを開始できます。
・デメリット
- 証人が必要になる
公正証書遺言を作成するためには、公証人以外に2人以上の証人を用意しなければなりません。証人は遺言の内容を知ることになります。 - 費用がかかる
公正証書遺言の費用は、財産の価額に応じて変わり、証人を2人手配する必要もあります。出張料や交通費なども別途必要になります。 - 時間がかかる
公正証書遺言を作成するためには、事前に遺言内容や必要書類を準備し、公証人と打ち合わせし、公証役場で遺言書を作成するという手続きが必要です。これには数日から数週間かかる場合もあります。
公正証書遺言を作成する6つの流れ

1.遺言者(依頼者)との面談
作成動機や内容を確認します。 遺言者(依頼者)の財産内容や相続人を確認し、ご希望内容をお伺いします。
2.必要書類の蒐集
遺言者の財産や財産を残したい相続人や受遺者の書類を蒐集します。
| 書類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 備考 |
| 遺言者の印鑑登録証明書 | ○ | △ | 公正証書遺言作成時に発行後3ヶ月以内のものが必要 |
| 依頼者の補助証明書 | ○ | △ | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
| 「相続させる」場合、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本等 | ○ | △ | |
| 「遺贈」する場合、受遺者の住民票 | ○ | △ | |
| 金融資産の資料(メインバンクの通帳の見開きページ、直近の残高の写し等) | ○ | ○ | 遺言書に記載する金融資産に関するもののみ |
| 直近の固定資産税納税通知書(財産に不動産がある場合) | ○ | ○ | 履歴事項全部証明書の請求と公正証書遺言の手数料計算に使用する。納税通知書が見当たらない場合は「固定資産税評価証明書」を請求する。 |
|
株券などの有価証券資料 |
○ | ○ | 証券証書等、保有内容が分かる資料 |
| 貸金庫の資料 | ○ | ○ | 銀行名・支店名・番号が分かる資料 |
| 証人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるもの | ○ | × | 依頼者が証人を選任する場合 |
| 遺言執行者の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるもの | ○ | ○ | 依頼者が遺言執行者を専任する場合。ただし、相続人を遺言執行者に指定する場合は不要 |
| その他動産など | 必要に応じて遺言者へご案内 |
3.遺言書文案作成
遺言書文案作成 原案を作成し、依頼者様へ提示します。
また事前に公証役場へ文案を確認してもらうことも可能です。修正箇所があれば修正し、依頼者様の承認を得ます。
4.証人の準備
遺言者の友人等に依頼する方法、公証役場に依頼する方法 (1名につき10,000円程度)、当事務所にて提携のある 士業に依頼する方法があります。
5.公証人と打ち合わせ
必要書類一式と遺言書の文案を作成したら、公証役場に事前確認を依頼します。
後日公証役場から連絡が入り、遺言書案と公正証書遺言作成の見積書が届きます。内容に問題がなければ、公証役場と遺言書作成日の日程調整をします。
6.遺言者(依頼者)による遺言書の内容把握
公証役場では、遺言者が公証人の前で遺言書の内容を口頭で伝えます。公証人がその内容を筆記し、公正証書として作成します。
一言一句伝えないといけないということではなく、『ご自宅不動産はどうしますか?』、『預貯金はだれにあげますか?』など遺言者が回答しやすいように進めてくれます。
とはいえ、回答できないと当日遺言書の作成ができないこともありますので、事前準備はしっかりおこないましょう。
7.作成当日
待ち合わせ時間の確認と実印、印鑑登録証明書の持参を依頼者様へお願いする。 待合室にて文案の再確認をします。
その後面談室にて公証人が遺言者(依頼者)と証人の本人確認をします。
公証人が作成した遺言書の内容を遺言者に質問しながら読み上げます。遺言内容にその都度間違いないか確認し、問題がなければ本人と証人が署名・捺印します。
※遺言書は3種類(原本・正本・謄本)作成されます。 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。 正本は遺言者に交付され、謄本は証人に渡されます。
最後に公正証書遺言の作成手数料を支払って完了となります。
作成の段階で『公証役場』での事前チェックも入りますので、無効になる可能性はほぼないと見ていいと思います。
ただ作成には必要書類の蒐集や原案の作成とかなり手間と時間が必要になるのも事実です。
弊所では、ご相談者様に寄り添い、最大限ご希望通りの遺言書が作成できるよう尽力いたします。お気軽にご相談ください。
↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。
下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。