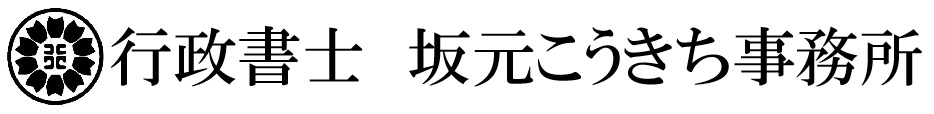会社の種類

会社にはいくつか種類がありますが、代表的なものに『株式会社』と『合同会社』があります。
『合同会社』は『株式会社』をさらに小さくしたようなイメージで、小規模の事業をするのに向いています。(とはいえ、合同会社にもボーズやアマゾンなど大きな会社もあります)どちらも登記が必要な点では同じですが、コストや組織の構成などが異なります。
『株式会社』と『合同会社』の違い

| 定款の認証 | 登記 | 設立費用 | 知名度 | 事業拡大 | |
| 株式会社 | 必要 | 必要 | 22万円~ | ある | 小規模から大規模まで可 |
| 合同会社 | 不要(定款の作成は必要) | 必要 | 6万円~ | あまり知られていない | 小規模の事業 |
『株式会社』と『合同会社』は共通点も多いですが、広く一般に知られているのは圧倒的に『株式会社』です。合同会社は費用が安くすむというメリットがありますが、『株式会社』に比べれば認知度も低いでしょう。登記されている会社の形態も圧倒的に『株式会社』が多いため、特に理由がなければ『株式会社』がおすすめです。
会社設立のスケジュール

会社は法務局に登記(登録)をすることで『法人』として認められます。つまり登記をすることで、会社名義で契約を行ったり、銀行に口座開設が出来るようになります。
個人事業主の場合は、税務署に開業届を出せばよいのですが、会社の場合は、さまざまな書類を作成し、定款の認証や登記の申請といった一定の手続きを経なければなりません。なお弊所では提携先の司法書士へ登記手続きを依頼していますので、ワンストップで手続きが完了します。
・設立登記までのおおまかな流れ
| 会社の基本事項を決定します ↓ |
| 定款を作成します ↓ |
| 定款を公証役場で認証してもらいます ↓ |
| 登記に必要な書類の作成と準備をします ↓ ※提携先の司法書士対応 |
| 設立登記を法務局に申請します ↓ ※提携先の司法書士対応 |
定款作成から会社設立手続き完了まで

- 定款の認証
会社は株主などがお金を出し、役員が事業を運営することで発展していきます。したがって、複数の関係者が関わってきます。そこで、会社に関する一定の約束事を決めたものを『定款』といいます。また定款は作成したのち、『公証役場』で正しく作成されていることを確認してもらう必要があります。これを定款の認証といいます。 - 設立登記
会社を設立する際には、定款を作成、認証後に法務局で『設立登記』が必要になります。これは簡単にいうと法務局に会社の重要な情報を登録することです。なお会社の設立日は法務局へ設立登記申請を提出した日となります。 - 各種届出(新規設立の場合)
会社を運営していくためには、諸官庁に手続きが必要になります。会社を設立後、その旨を税務署、年金事務所などに速やかに届け出ます。提出の期限はそれぞれ異なる為、遅れることのないように注意しましょう。なお、登記が完了していなければ登記事項証明書が取れない為、銀行での口座開設は登記完了後となります。 - 手続きは1ヶ月程度かかる
会社を設立するには色々と決めなければならないことや用意しなければならないものがある為、思いのほか時間がかかります。設立登記の準備にすべての時間を注ぐことが出来ない場合もあるでしょうし、公証役場や法務局で手続きをしなければならないので、やることがたくさんある中で自分の思い通りに進まない場合もあります。
設立登記を法務局に申請するまでの準備期間を2週間、法務局に登記の申請をしてからその後の諸手続きに1~2週間程度見ておきましょう。法務局に設立登記を申請してから、その申請内容の審査が行われます。不備がなければ、3日から1週間前後で審査は完了します。
・窓口別手続き早見表
|
手続きする役所 ----- タイムテーブル |
公証役場 | 法務局 | 市区町村 | 税務署など | 年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク) | 金融機関 |
| 会社設立登記の前 | 定款の認証 |
・事業目的の確認 |
・発起人(出資をする人)と役員の印鑑登録証明書の取得 | 出資金の払込み(個人口座) | ||
| 会社設立登記 | ・設立登記の申請 ⇒会社の設立日 |
|||||
| 会社設立登記の完了後 | ・登記事項証明書の取得 ・印鑑カードの取得 ・会社の印鑑証明書の取得 |
・従業員の住所地ごとに特別徴収義務者の変更届 | ・設立時に必要となる各種届出書の提出(設立から1ヶ月以内) | ・年金事務所へ各種届出書の提出(設立から5日以内) ・労働基準監督署への各種届出書の提出(労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内) ・公共職業安定所(ハローワーク)へ各種届出書の提出(設立した日田費の翌日から10日以内) |
・会社名義の口座の開設手続き ・資本金を会社名義の口座に振り替える |
会社設立にかかる費用

株式会社を設立するときに最低限必要となる主な手続き費用は次の3つになります。これらは、専門家に依頼しても自分で手続きしても必ずかかる費用です。
- 定款(会社の規則集)を認証してもらう費用
- 設立登記をするときの登録免許税(登記にかかる税金)
- 会社の登記事項証明書(会社の基本事項が記載されている証明書)、印鑑証明書の取得費用
・会社の設立にかかる費用の一覧
| 手続き | 窓口 | 項目 | 費用 | 備考 |
| 定款の認証 | 公証役場 | ・認証手数料 ・収入印紙 ・定款の謄本手数料(5枚とした場合) |
・3~5万円※資本金による ・4万円(電子定款なら不要) ・1,250円 |
電子定款の認証をした場合は、収入印紙代は不要。定款の謄本代は、1枚250円×枚数分。定款の謄本は登記申請時に使用する |
| 設立登記 | 法務局 | ・登録免許税 | 15万円 | 資本金の額の0.7%で、その額が15万円に満たない場合は一律15万円 |
| 登記が終わったあとの書類取得 | 法務局 | ・会社の登記事項証明書(3通取得した場合) ・会社の印鑑証明書(1通取得した場合) |
・1,800円 |
登記事項証明書は1通600円(ただしオンラインで取得した場合は、1通500円) 印鑑証明書は450円 |
| その他 | 会社の印鑑作成費(会社の実印のみ作成した場合) | 1,300円~ | ネット通販で手配すると安い | |
| 合計 | 22万4,800円~ | |||
※電子定款に対応した行政書士に定款作成・認証を依頼すると、紙の定款と違って印紙代40,000円がかかりません。お得に作成できる上に、忙しいご依頼者様に代わって公証役場との手続きも代行致します。
登記までの流れ

・定款認証が終わってから登記までの流れ
| 出資金の履行(資本金の払込み)↓ |
| 登記に必要な書類と登記申請書を作成↓ |
| 書類の最終チェック↓ |
| 登記の申請↓ |
| 不備があれば補正する↓ |
| 登記の完了(申請して3日~1週間前後)↓ |
| 会社の登記事項証明書、印鑑証明書を取得 |
会社設立の登記申請は、代表取締役が会社を代表して行います。登記申請書を提出して不備がなければ、3日から1週間前後で審査が完了します。完了すれば会社が無事成立したことになり、会社の創立記念日にあたる設立日は、会社設立登記を申請した日になります。つまり登記が完了した日ではなく、法務局の窓口に申請書を出した日が会社設立の日として登記されることになります。会社の創立記念日を大安の日や1日など、きりのいい日やぞろ目の日など特定の日にしたければ、その日に設立登記申請を行う必要があります。
登記する事項について

定款で定めた全ての事項を登記する必要はなく、法令の規定により登記しなければならない事項または登記できる事項を記載します。会社設立の場合は主に次の事項を登記します。
・登記する事項一覧
| 1.商号 |
| 2.本店住所 |
| 3.公告の方法 |
| 4.目的 |
| 5.発行可能株式総数 |
| 6.発行済株式総数(設立時に発起人に割り当てる株式の合計数) |
| 7.資本金の額 |
| 8.株式の譲渡制限に関する規定(設定した場合) |
| 9.役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名、監査役の氏名) |
| 10.取締役会の設置、監査役の設置(取締役会を置く会社の場合) |
その他、支店を置いた場合、会社の存続期間または解散の事由を定めた場合、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する場合などは、その旨を登記します。
変更事項を登記しなかったり、嘘の登記をしたら?
会社は登記をする義務があるので、登記をした内容に変更がある場合は、その都度、登記をし直さなければなりません。第三者が登記事項証明を取得した際に、最新の会社の情報がわからなければ、円滑で安心な取引に支障が出るからです。
会社の登記の多くは登記期間が決まっており、一定の期間内(変更の日から2週間以内が多い)に登記の変更事項の申請をしかければ、100万円以下の科料の制裁を受けることがあります。また許認可についても役員の変更など登記内容の変更がある場合、登記の変更完了後に変更届を2週間から1ヶ月以内に出す必要があったりとかなり時間がありません。変更が発生する予定が分かった時点で早めの対応を心掛けましょう。
資本金の払込み

定款の認証が終わったら、会社の資本金を発起人の個人口座に振込または入金します。会社の資本金を個人口座に振込、入金する理由ですが、この段階ではまだ会社の登記が完了していないので、会社の口座を金融機関で開設することはできないからです。発起人が複数いる場合は、1名を発起人の代表者と決め、その代表者の個人口座に振込または入金します。
資本金を振り込むための個人口座は新たに開設する必要があるのか?
ここで使用する口座は、定款の認証が終わってから会社が成立して会社の口座を開設するまでの間、一時的に会社の資本金をプールしておく」だけなので、すでに持っている口座の一つを利用しても構いません。ただし、個人としての使用分ときっちり分けておく必要があるので、会社設立用に新たに口座を開設するほうがわかりやすいです。注意しなくてはいけないのは、発起人以外の第三者の口座に会社の資本金を振込・入金しても、会社の資本金の払込みとしては認められないので、必ず発起人の個人口座を利用してください。
※個人事業を行っていた人が法人成りする際に、個人事業時代の屋号名義の口座を利用することは登記の際に認められないことが多いので、個人名義の口座を利用します。
資本金の払い込み時期について

具体的には、『定款で発起人が設立時に引き受ける株式の数を定めるため、定款の作成日以後の日であれば問題ない』ということになります。順番が前後して間違うと大変なので、定款の認証をした後に払い込みをすれば問題ないでしょう。
資本金払い込み方法と注意点

・発起人が1人の場合
発起人が1人であれば、発起人自身の口座に会社の資本金の額を入金(預け入れ)します。入金(預け入れ)は振込とは違って、通帳にお金を入れた人の氏名が記帳されませんが、発起人の口座に発起人自身がお金を入れたことがわかるので問題ありません。もちろん、発起人の氏名が記帳されるように振込をしても構いません。
・発起人が複数の場合
発起人が複数であれば、設立時に引き受ける株式に応じた資本金の額を、発起人代表者の口座にそれぞれ振込んでもらいます。発起人代表者が他の発起人から出資額を預かって、まとめて入金するやり方でも構いませんが、それぞれの名前と出資額が通帳に印字されるように、各人に振込んでもらったほうがわかりやすくなります。
・発起人以外の名前による振込・入金
発起人以外の名前による振込・入金は登記の審査で認められないので、発起人が経営する別会社名での振込や家族の名前での振込はしないようにします。
・振込・入金時期について
通帳に残高があるだけでは登記は通らないので、定款の認証を受けた日以後に、新たに入金または振込をする必要があります。発起人の個人口座を利用するので、単に残高があるだけでは、そのお金が設立する会社に対する出資金なのかどうか分からないため、定款認証以後の日付で入金または振込をします。
資本金の払込証明書の作成
会社設立時の取締役になっている人は、発起人からなされた資本金の振込や現物出資の調査をします。具体的には、出資が金銭だけなら発起人代表者の個人口座二資本金全額の入金または振込がなされているかを確認します。現物出資がある場合は、検査役の選任を要する場合を除き、定款に記載または記録された価額が相当であるかの調査や、弁護士や税理士、公認会計士などによって現物出資財産に関する証明がなされているときはその証明が相当であることの調査が必要になります。
・資本金の払込証明書の作成
設立時の取締役などによる調査が終了したら、資本金の払込があったことの証明書(払込証明書)を作成します。払込証明書は、資本金の払込がされた発起人代表者の通帳のコピーと一緒にホチキスでとじます。通帳のコピーは、通帳の表紙、支店名などの記載がある裏表紙、払込の記録が印字されている貢の合計3貢(払込の記載が数貢にわたる場合は該当貢全て)のコピーをとります。用紙はA4縦サイズでコピーをとり、左側はホチキスでとめやすいように、3~4cmあけておきます。

設立登記で必要な書類の確認

登記を申請する際には、まず登記申請書を作成する必要がありますが、登記申請書の他にもいくつかの書類を一緒に添付して申請しなければなりません。『定款』や『払込を証する証明書』も添付書類のひとつです。書類に不備があると、修正をするために法務局へ再度出向かなければならなかったり、後日再提出することになったりして、審査の期間が延びてしまいます。また、修正できないようなミスであれば、一度申請を取り下げて、再度申請をしなければいけないこともあります。再申請になると会社設立日が変わってしまうばかりか、納めた登録免許税の還付手続きをしなければならなかったりと、余計な手間がかかってしまいます。また、書類ごとに署名押印する人が異なりますので、誰がどの印鑑を押すのかも注意が必要です。
・必要書類一覧表(取締役会を設置しない会社)
| 用意する書類 | 署名または署名捺印者 | 印鑑 | 備考 | |
| 1-1 | 登記申請書 | 代表取締役 | 会社実印 | |
| 1-2 | 登録免許税納付用台紙 | |||
| 1-3 |
CD-R、DVD-Rなどの電磁的記録媒体 |
※書類を印刷せず、電磁的記録媒体で提出する場合 |
||
| 2 | 定款 | 発起人 | 個人実印 | |
| 3 | 発起人の決定書 | 発起人 | ||
| 4 | 取締役の就任承諾書 | 取締役 | 個人実印 | |
| 5 | 代表取締役の就任承諾書※1 | 代表取締役 | 個人実印 | |
| 6 | 取締役全員の印鑑証明書 | |||
| 7 | 払込を証する証明書 | 代表取締役 | ||
| 8 | (取締役などの調査報告書) | 取締役 | ※2 現物出資がある場合のみ | |
| 9 | (資本金の額の計上に関する証明書) | 代表取締役 | ※2 現物出資がある場合のみ | |
| 10 | 印鑑届出書 | 代表取締役 | 会社実印、個人実印 | |
| 11 | 印鑑カード交付申請書 | 代表取締役 | 会社実印 |
※1 取締役が1名の場合は、自動的にその人が代表取締役二なる為、代表取締役の就任承諾書は不要です。
※2 現物出資が500万円を超える場合は、裁判所に検査役の選任を申し立てるか、弁護士や税理士の証明書などが別途必要です。
登記申請書の作成(取締役非設置・現物出資の場合)

登記申請書は法務局のサイトからダウンロードできます。(URL:法務局申請様式)また、登記・供託オンライン申請システムを利用して登記申請をすることもできます。QRコードが印字され、このQRコード付き書面申請をおこなうと、インターネット上で登記の処理状況を確認できたり、必須項目の入力漏れを確認する機能もある為、より正確に申請書の作成が可能です。詳しくは法務省のサイトをご確認ください。(URL:QRコード書面申請)
- 登記の事由
『登記の事由』は、発起設立の場合は『令和○年○月○日発起設立の手続き終了』と記載します。『発起設立の手続きが終了した年月日』は、通常は取締役が行う出資の履行の調査などが終わった日になるので、『払込を証する証明書』に記載した年月日を記入します。そして、発起設立の手続きが終了した年月日として記入した日から2週間以内に登記の申請を行います。 - 登記すべき事項
『登記すべき事項』は、登記申請書の中で最も重要な部分です。ここに記載または記録している内容通りに登記がされます。『登記すべき事項』に記入した内容が登記に反映されるので、会社の商号や目的などは定款に記載してあるとおりに、役員の住所・氏名については印鑑証明書に記載してあるとおりに正確に記載します。実務上は、実際の申請書には『別添CD-Rのとおり』と記載し、別途CD-RやDVD-Rなどの電磁的記録媒体に入力したものを提出します。また、オンラインによりあらかじめ情報を提出することも出来ます。その場合は、『別紙の通りの内容をオンラインにより提出済み』と申請書に記載し、送信後に届いた『到達通知書』を印刷して登記申請書などとともに提出します。 - 課税標準金額
『課税標準金額』とは、登録免許税を算出する元になる金額で、設立の場合は『資本金の額』を記載します。桁が大きい場合は『億』『万』などの単位を示す文字を用いて構いませんが、『千』は使用しません。例えば、300万円、300万5,000円といった書き方をします。 - 登録免許税
登記の時にかかる税金である『登録免許税』は、『資本金の額の1,000分の7(0.7%)』となります。算出した額が15万円に満たない場合は15万円となります。登録免許税は、あとから納めるのではなく、登記の申請のときに納めます。登録免許税を納めなければ、いくら書類が揃っていても登記は完了しません。 - 申請年月日、申請人
申請人として会社の本店(住所)、商号、代表取締役の住所・氏名を記載します。補正がある場合、連絡をもらえるように連絡先電話番号も記入しておきます。連作先電話番号は日中連絡が取れる番号を書きます。携帯の電話番号でも構いません。 - 申請先法務局名
最後に申請書を提出する法務局名を記載します。会社の本店が福岡市中央区にある場合は、福岡法務局が管轄になるので、『福岡法務局御中』と書きます。
登録免許税の納付について

『登録免許税は』は『収入印紙』で納めます。法務局の窓口で、現金で登録免許税を支払うことはできないので、収入印紙を購入して台紙に貼り付けておきます。登記申請書に貼り付けてもかまいませんが、登記申請書に不備があって差し替える場合に支障があるので、別に台紙を用意します。台紙はA4のコピー用紙でもかまいません。台紙となる紙を用意し、真ん中あたりに収入印紙を貼ります。収入印紙は郵便局で購入できるほか、法務局内の印紙売り場でも購入できます。登記申請書と登録免許税納付用台紙は、他の添付書類と一緒にホチキスでとじ、登記申請書と登録免許税納付用台紙との継ぎ目に会社実印で契印します。
書面申請とオンライン申請について

申請方法は、書面申請とオンライン申請の2つがあります。オンライン申請の方が迅速ではありますが、電子証明書を持っていて申請用総合ソフトを利用できる場合に限られます。環境が整っていない人にとってはハードルが高く、機器を一から揃えるために費用と手間がかかるため、書面申請の方が簡易です。書面申請の場合は、登記すべき事項を『事前に登記すべき事項をオンラインで提出』とCD-RやDVD-Rなどの『電磁的記録媒体で提出』で提出の2パターンあります。
『事前に登記すべき事項をオンラインで提出する方法』について
『登記すべき事項』はそこに記載している内容どおりに登記がされるため、登記申請書の中で最も重要な部分です。登記すべき事項を登記申請書にそのものに入力して申請すると、法務局で一から入力しなおさなければらず、非常に処理スピードが落ちてしまいます。また、人の手によるものなので入力ミスも出てしまいます。そこで実務上は、CD-Rなどの電磁的記録媒体に記録して提出する方法か、事前に登記すべき事項をオンラインで提出する方法のいずれかによって、簡易迅速に登記を進めることになっています。オンラインで提出する方法は、ソフトのダウンロードが必要となるので、詳細は法務局の『登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について』を参考にしてください。(URL:法務省:登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について)
発起人の決定書

発起人の決定書とは、株式会社を設立する際に必要な書類の一つです。この書類は、会社設立に関する基本事項を発起人が決定したことを証明するために作成されます。具体的には、以下のような内容が記載されます。
-
商号(会社名)
-
本店所在地(番地まで含む住所)
-
発行可能株式数や設立時発行株式数
-
資本金の額
-
設立時取締役の人数と氏名
-
電子公告の場合のサイトURL
発起人の決定書は、定款に記載されていない詳細事項を補足する役割を果たします。例えば、定款では本店所在地が市町村までしか記載されていない場合、発起人の決定書で番地まで明記する必要があります。
就任承諾書

設立時の取締役、代表取締役、監査役(以下まとめて「設立時役員という」につき、それぞれの「就任承諾書」を作成します。
発起人が設立時役員を選び、設立時役員が就任を承諾することで、設立時役員が決定します。
取締役が1名の場合は、自動的にその人が代表取締役になるので、代表取締役としての就任承諾書はなくてもかまいません(代表取締役の承諾書を作成しても支障はありません)。しかし取締役が複数いて、その内の1名を代表取締役とした場合は、代表取締役になった人は取締役としての地位と代表取締役としての地位を有するので、それぞれに就任承諾書を作成します。単に代表取締役の就任承諾書のみを作成するだけでなく、取締役の就任承諾書もあわせて作成しましょう。
就任承諾書に押す印鑑について
取締役会を置いていない会社の場合は、取締役の就任承諾書に「取締役個人の実印」を押します。
取締役会を置いている会社の場合は、代表取締役の就任承諾書に「代表取締役個人の実印」を押します。それ以外の取締役および監査役の就任承諾書は、個人の認印でも差し支えありませんが、就任承諾書は本人の就任の意思確認をする書類なので、「実印」を押すのが望ましいです。
資本金の額の計上に関する証明書

払い込みをした資本金の額を法律に従って計上したことに関して、設立時代表取締役が証明書を作成します。会社設立の際に出資する財産が金銭のみの場合は、会社計算規則により資本金の額の計上に関する証明書の作成は不要です。金銭で出資をした額、現物出資をした額をそれぞれ記載し、合計額が会社の資本金となります。
印鑑届出書
個人と同様に会社も印鑑を実印登録します。実印として届け出た印鑑は今後、登記申請書やそのほかの添付書類に押印することになります。会社の実印が登記申請書などに押印されていれば、会社からの申請で間違いないと法務局は判断します。会社の実印は、会社の代表者である代表取締役が届出をします。
印鑑届出書は設立登記の申請書と一緒に提出します。会社設立の登記の場合、登記申請書の添付書類として代表取締役個人の印鑑証明書添付しているので、印鑑届出書に別途添付する必要はありません。
印鑑届出書の左上に実印を押印する欄があります。ここに押印した印鑑が登録されるので、押印する際に印影が欠けたり不鮮明になららないように印鑑の向きにも注意しましょう。

書類をとじる順番について
書類の作成が終わったら、次に書類を順番にとじていきます。書類には並べる順番があります。順番通りに並べていなかったら登記が通らないわけではありませんが、法務局が審査しやすいように次の順番でとじていきます。
一番上に登記申請書がくるようにして、登録免許税納付用台紙、定款などの添付書類一式と続きます。これらの書類をまとめ、左側2ヶ所をホチキスでとじます。ただし印鑑届出書はホチキスでとじないでクリップで留めるだけにします。CD-Rなどの電磁的記録媒体は書類と一式で提出します。
なお添付書類は原則、原本を提出します。補正の場合など手元に資料があった方がわかりやすいので書類一式すべてコピーを取っておきましょう。
・書類をとじる順番
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙 ※登記申請書と契印する
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書 ※取締役が1人の場合は不要
- 取締役全員の印鑑証明書
- 出資の払い込みを証する証明書
- 印鑑届出書

| 最終チェック |
| 1.登記申請書と登記すべき事項に正確な記載をしているか |
| 2.登記申請書と登録免許税納付用台紙には会社実印で契印をしているか |
| 3.各書類に押印する印鑑は、会社実印、個人実印を間違えずに押印できているか |
| 4.就任承諾書は人数分あるか |
| 5.印鑑証明書は3ヶ月以内に取得したものか |
| 6.出資の払い込みを証する証明書は、通帳のコピーと一緒にとじているか |
| 7.登記申請書、登録免許税納付用台紙と添付書類一式は左側2箇所をホチキスでとじているか |
| 8.印鑑届出書は登記申請書にクリップで留めているか(ホチキスでとじない) |
また手続き先の公証役場等も平日の日中に行かなければなりません。
弊所では会社設立へ向けてお忙しいお客様に代わり、面倒なお手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。