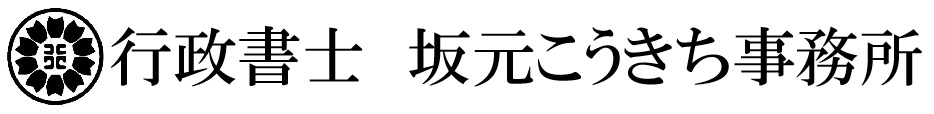自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、その名の通り、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。
自筆証書遺言は他の遺言に比べても費用も手間もかからない為、最も気軽に作成できる遺言書です。
その反面、法律で定められた一定のルールや相続手続きを考慮しないと法的に無効になったり、 遺言書の内容が原因で、相続人間での争いを引き起こす可能性もあります。
また、自筆証書遺言は一つしか存在しない為、紛失したり、不正に開封されたり、改ざんされたりすると 取り返しのつかないことになります。
自筆証書遺言を有効にする為の要件は下記の5点です。
1.全文自書
2.日付の自書
3.氏名の自書
4.押印
5.加除その他の変更
自筆証書遺言を作成する場合は、これらの要件を全て満たす必要があります。 どれか一つでも欠けてしまうと遺言は無効になってしまいます。
1.全文自書

全文とは実質的内容部分でいわゆる本文にあたります。
自書が要求される理由は筆跡によって本人が書いたものとして判定でき、自筆ということが分かれば遺言の内容が真意であると推測できるからです。
つまりWordやワープロで作成された遺言は無効です。 ただし、法改正によって、財産目録の部分については自筆以外の方法(ワープロなど) が認められました。
2.日付の自書

遺言は複数ある場合、一番新しいものが効力ある遺言とされます。
また遺言作成時に作成者が遺言を作成する能力があったのかを判定しますので 日付の自書が要求されているのです。
年月のみで日付のない場合、または○年○月吉日などは無効です。
3.氏名の自書

氏名の自書が要求されるのは遺言の作成者を明確にし誰の遺言なのか明らかにする為です。
また自筆で記載することによって遺言作成者本人の真意を証明する為です。 本人と識別できる名前なら、氏名は戸籍上のものでなく通称でもかまいません。
4.押印

押印が要求されるのは、氏名の自書と同じです。
実印でも認印でもかまいません。 ただ実印があるなら実印がいいでしょう。
5.加除その他の変更

加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を附記して 特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印をおさなければならないと定められています (民法968条3項)。
つまり訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。
なお、この方式に則っていない訂正等は無効になりますが、遺言までは無効にはなりません。
自筆証書遺言のメリット

1.費用がかからない
2.手軽に作成できる
3.遺言の内容を誰にも知られずに作れる
専門家と一緒に遺言書を作成することは、いくつかのメリットがあります。 一つは、お客様の希望に沿った法的に有効な遺言書を作成できること。
また、遺言に残したい 内容が法的に可能なものかどうか、専門的なアドバイスが得られること。
そして、相続手続きも専門家にお任せできること。これらのメリットにより、遺言書作成のリスクを 最小限に抑えることが可能です。
自筆証書遺言のデメリット

1.要件を満たしていないことで無効になる恐れ
2.意思能力で争いになることがある
3.相続開始後に家裁の『検認』が必要(法務局に保管している場合を除く)
自筆証書遺言は、要件を満たしていないとせっかく作成しても意味をなさなくなる可能性があります。
また自分が亡くなった後に作成した遺言書が発見されない、悪意のある相続人が破棄するなどの可能性もあります。
遺言書は自分の最終意思を残された家族に伝えるための有効なツールです。
発見されない、無効になってしまったなど、不本意な結果にならないよう、行政書士などの専門家に相談してみましょう。
自筆証書遺言を作成する5つの流れ

1.遺言に書きたい財産の洗い出し
遺言に書きたい財産の洗い出し まずはどんな財産があるのか、ある程度の評価額を出します。
遺言書に書ける主な財産はこれらです。
不動産、現金・預貯金(普通預金・定期預金) ・株式 ・投資信託、生命保険、自動車や貴金属等。
2.財産資料を集める
遺言に書く財産が把握できたら、それらの資料を 集めていきます。
| 財産の種類 | 内容 | 主な証明資料 |
| 不動産 | 土地・建物(自宅、賃貸物件など) | ・登記事項証明書(登記簿謄本) ・固定資産評価証明書 ・名寄帳 |
| 預貯金 |
銀行口座残高 |
・残高証明書 ・通帳コピー ・取引明細書 |
| 現金 | 手元にある現金 | ・遺品整理時の現金記録 ・相続人の申告 |
| 有価証券 | 株式、投資信託、債券など |
・証券会社の残高証明書 ・取引報告書 ・年間取引報告書 |
| 自動車 | 登録された車両 | ・車検証 ・自動車登録事項証明書 ・査定書類 |
| 動産 | 宝石、貴金属、骨とう品など | ・鑑定書 ・購入時の領収書など |
3.財産をあげたい人を決める
財産の資料が集まったら、あとは財産をあげたい 人を決めていきます。
自分の財産を引き継ぐ人ですから、じっくり時間を かけて考えましょう。 ご自身の家族や親族に限らず、推定相続人以外の 第三者に財産をあげる(遺贈)こともできます。
4.遺言書を書く
遺言書を書く 準備ができたら、あとは遺言書を書くのみです。
用紙に決まりはありませんので文房具屋で便箋を 購入してもいいですし、自宅にある白紙でも問題ありません。
5.内容の最終確認
完成したら内容に不備がないか、民法の要件に従っているか 隅々までチェックしてください。
問題がなければ、あとは遺言書の保管先を決めます。 ご自身で保管をしてもいいですし、任せられる専門家や 家族に渡しておいてもいいでしょう。
なお、自筆証書遺言なら法務局で保管をすることができます。(遺言書保管制度) 保管場所に困ったら法務局の利用を検討しましょう。
作成の手軽さや、費用がかからない反面、民法の要件に満たして いない自筆証書遺言は無効となってしまう為、作成時に十分注意しましょう。
その反面、気を付けて書かないと要件不足で無効になったり、1通しか遺言書が存在しないために発見されない、破棄されてしまったなど思わぬ事態にならないともいえません。
弊所では、ご相談者様に寄り添い、ベストな遺言書作成をご提案いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。
↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。![]()
無料相談・お問い合わせ
無料相談・お問い合わせフォームへのご訪問ありがとうございます。
取扱い業務外のことでも、お気軽にお問い合わせください。